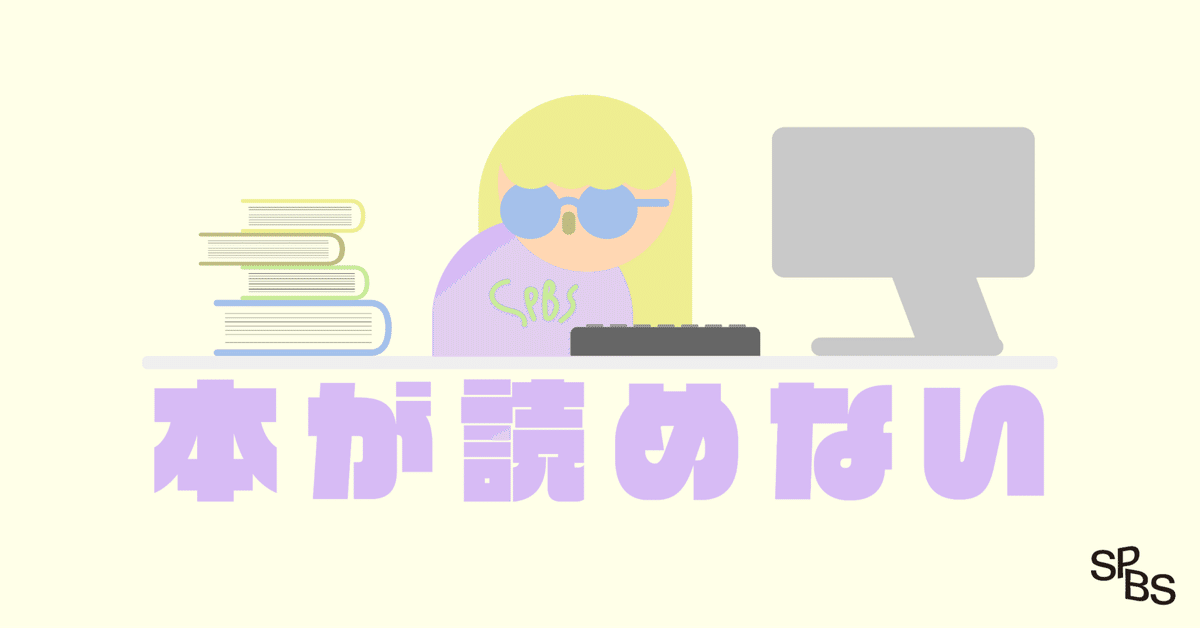
『虎に翼』世代の女子たちが夢中になって読んでいた、昭和5年のお宝雑誌を発掘
今期の朝ドラ『虎に翼』が、とてもおもしろい。
さまざまな場面で苦労を強いられる、強いられてもそんなものだと思って気づくこともない女性の立場の弱さに「はて?」と立ち止まって疑問を抱き、さまざまな困難を乗り越えながら、法を力に立ち向かう女性たちが、とてもかっこよい。かつては司法試験すら受けられなかった、裁判官にはなれなかった、育休制度もなかった、結婚すれば「無能力者」という立場だった“無数の彼女たち”の営みが積み重なっていまがあるのだと思うと、心から「ありがとう」と言いたくなるし、まだまだ積み残されたものごとに対して、私たちも諦めてはいけないのだと思わされる。
このドラマの主人公の寅子や、同級生の花江たちが女学生だった昭和初期に、若い女子たちに人気を博していた雑誌が『令女界』だ。そしてつい最近知ったのだが、私の祖母は、その編集者だったそうだ。私の記憶の中の祖母は、いつも地味な色の和服を着た、当時としては背の高い、しゃんとした人だ。小さいころは、祖母とは正月くらいしか会わなかったし、晩年に同居した約5年間はすでに認知症になっていたので、若くして夫を亡くし、住み込みの寮母をしながら女手一つで4人の幼い子どもを育ててきた苦労人の祖母に、そんな過去があったことは全く知らなかった。
親戚の法事でその話を耳にしたとき、いま自分が編集者として働いている偶然に驚き、祖母が編集していたという雑誌が一体どんなものだったのか、とても興味が湧いてきた。親戚が祖母から伝え聞いた話によると、『令女界』はあまりの人気ぶりで、女学校では持ち込み禁止令が出されたほどだったという。見たい。読んでみたい。でもそんなものは、もちろんAmazonを探したって、町の古本屋に行ったって、見つからない。戦争の時代を挟んでしまっているから、昭和初期のバックナンバーを見つけるのは相当難しいはずだ。
あまり大きな期待はしないまま、私はメルカリを検索してみた。すでに売り切れた雑誌が数冊。雑誌の付録だった竹久夢二の絵葉書がぽつぽつと。あとは、令女の言葉に引っ張られた怪しげな何かが数点。やはり簡単には見つからないか、と諦めつつ、検索キーワードを保存しておいた。
数週間後、そのキーワードに、一冊の雑誌がヒットした。まぎれもない『令女界』、昭和5年発行の2月号。『虎に翼』の寅子や花江たちが16歳の頃だ。もしかしたらちょうど祖母が編集に関わっていた時期かもしれない。ドキドキしながら、購入ボタンをタップした。

届いた冊子はA5サイズ、ヘリはもうボロボロで、開くと崩れてしまいそうだったけれど、元の持ち主の方の感想がブルーブラックの万年筆で丁寧にメモされていたりして、その時代にその方も、この雑誌も、たくさんの読者も生きていたのだという確かさが伝わってきた。
Wikipediaによると、『令女界』は大正11年創刊で、昭和25年に休刊。男女の恋愛を描いた小説も掲載されたため、ほかの少女雑誌よりも軟派なものとされていたそうだ。刊行中、かの川端康成や萩原朔太郎、小川未明などが著者として、挿絵には竹久夢二や、後の手塚治虫や高畑勲などにも影響を与えた蕗谷虹児も名を連ねている。
学校で禁止されていたなら、先生に見つからないようにカバーをかけてこっそりカバンにしのばせ、放課後に友達と貸し借りなんかをしたのだろうか。
読者の女子たちは、「ビルヂングに通ふ職業婦人にならうと考へた」モテ女子が妻子ある男性に戀してみたり、「十四歳で香水の匂ひ」を知った妹の奔放な生き方に、地味な姉が翻弄されたり、事務仕事の終わり頃に回ってきた傳票の端に今夜のデートの誘いが書かれていたりと、自由でモダンな生き方を描写した小説たちに、憧れや嫌悪などのいろいろな感情を募らせただろうし、「メイ牛山の美爪術」を真似してやすりで爪を磨いただろうし、海外ニュース欄でロンドンの働く女性たちの動向に刺激を受けただろうし、ネタバレ満載の洋画・邦画の写真つきあらすじ紹介に心躍らせたことだろう。
小さな版面に文字も絵もぎっしり詰まった雑誌は、きっといまのスマホくらい、乙女たちの手と目を離さない世界の窓だったに違いない。
驚いたのが、「読者文藝」の充実ぶりだ。散文、短歌、詩などが選評とともに約20ページにわたって掲載されている。いまでいうnoteの創作大賞の女子誌面版か。それが年に1回ではなく毎月募集されている。そして宛先は、「東京市外大森 令女界編集部」。番地なしで届くほど、毎月たくさんの封筒がここに送られてきたのだろう。
編集後記の欄に、もしかしたら祖母の名前があるかもしれない、と、ボロボロの紙が崩れないようにそっとページをめくり進めてみたが、残念ながら個人の存在がわかるような記載はなかった。達筆できりりとした大柄な祖母が、赤鉛筆を持ってモダンガール小説を校正している姿はちょっと想像できないけれど。
雑誌はタイムカプセルだと思う。その時代の空気を取り込んだコンテンツに、その時代のニーズを反映した広告。開くとそこに閉じ込められていた空気が、目の前に広がってくる。
当時の女子の進学率は、今よりずっと低かったはずだ。恵まれた女子だけが女学生になれた時代。本当はもっと学びたい、と渇望していた人たちも多かったことだろう。この雑誌にはこんな半ページ広告も掲載されていた。
色々の事情で女學へ入れぬ方!
獨學で女學校程度の學力を得たい
方!はこの講義録で勉強なさいまし。
「高等女学標準講座」なるテキストブックだ。尋常小学校(当時の学校制度の小学校)を卒業した人なら誰でも読めて十分会得できるようになっているそうだ。
学びの機会も、職業も、書いたものを発表する場も、多様な情報を目にする手段も、当時に比べれば格段に豊かないま、さまざまな不自由があったゆえに、一冊の雑誌に撓め込まれた熱量には、打たれるものがあった。
私が編集の仕事についたのは、本当に偶然の連続でしかなかった。編集者になる人は、子どもの頃から本の虫だったり、作文が得意だったりする人が多いのだろうけれど、私は目の障害があって多感な時期に本が読めずに成人してしまった、圧倒的な欠落感を抱えて生きている人間だった。それなのに、編集の仕事についているなんて、自分が一番驚いているし、やってみると、誰かが伝えたいことを伝わる形に変換するやりがいや、思いもよらない未知の世界や人に出会える編集の醍醐味がとても好きになっている。祖母もこんなふうに、編集の仕事を楽しんでいたのだろうか。長野の女学生が、どうして東京の編集者になったのだろうか。もっと話をきいてみたかったなと、昭和5年のタイムカプセルを前に思いをはせた。
ちょうどいま、SPBSでは、一人一冊の雑誌をつくる「編集ワークショップ」を開催している。今年の受講生たちは、それぞれが日々思うこと、突き詰めて考えたいことなどをテーマに落とし込み、10月の発表会に向けて雑誌を制作中だ。どんなタイムカプセルが生まれるのか、とてもワクワクしている。
(編集WS 2024 アーカイブは現在も販売中!)
(編集部 K)

