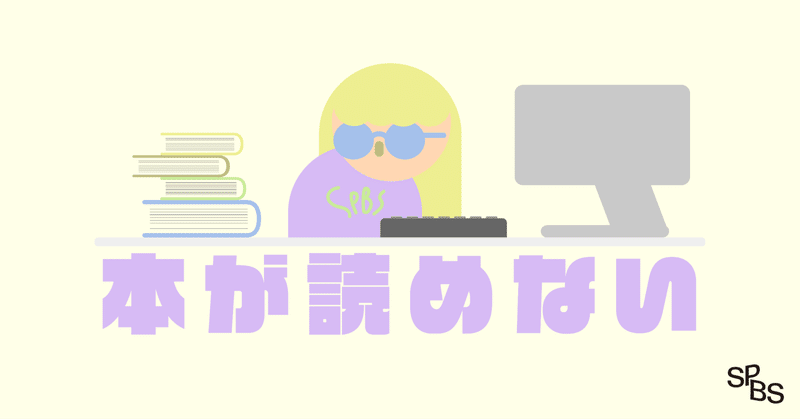
沈丁花の香りで思い出す亡き母とその母のこと
通りすがりにどこからともなく漂ってくる、甘酸っぱい華やかな香りを感じると、あぁ、またこの季節がやってきたなと思い出す。母の命日だ。
母が乳がんの2度目の再発で昏睡状態になったとき、私は研修でアメリカにいた。アメリカが他国に侵攻するかもしれない。報復テロに警戒せよ。そんなアラートが飛び交い、もしこのタイミングで一度帰国したら、そのときに保有していたビザでは再入国ができなくなるかもしれないと言われていた。そうしたら、今住んでいるニューヨークのアパートに残した荷物も、家賃の支払いもどうなってしまうのか。勝手の分からない中、取るものもとりあえず、一時帰国用の往復の航空券と、「その研修期間が終わったら必ず日本に帰国する」ことを証明するための、研修終了時の片道航空券をまとめて手配して、飛行機に飛び乗った。
帰国後すぐに向かった病室で、母は酸素か薬かなにかの吸入マスクをつけ、目を閉じたまま、白い病室で静かに呼吸を繰り返していた。たまに目を開けても、焦点の定まらない視線は空を泳ぎ、私のことも分からないようだった。
笑顔の華やかだった母は、カサブランカの花が好きだった。太く頑丈で真っすぐな茎に咲く大輪の白い花は、骨太でがっしりとした体躯と、控えめだけれど明るい顔立ちの母に似ている気がした。
その晩、私たちきょうだいは、病室に泊まることにした。夜中も交代で起きて、母のそばについた。私の番になった真夜中近く、突然母の両目が開き、光を取り戻した。声を発することはできなかったけれど、私たちは目で会話をした。母の片方の目から涙がすーっと溢れてきた。不思議と悲しみよりも、小さな子どもを寝かしつけるときのような、温かさが溢れてきて、ほほ笑みながら手のひらで母の頬をそっとなでた。
翌朝は春らしい晴れだった。かすかな望みをつなぐかのように、病室で小さくフジコ・ヘミングの「奇蹟のカンパネラ」のCDをかけた。ピアノの音のきらきらした粒が白い壁に差し込む光に反射する音と、心音を伝えるデジタルの音だけが舞っていた。
親を亡くすことは悲しいけれど、子を亡くすことはもっと悲しい。
祖父母が到着した。祖母は母の横に座り、その朝、庭で手折った沈丁花を吸入マスクに近づけ、「きみちゃん、あなたの好きだった花よ」と言いながら、香りを届けていた。
私は言葉を失った。
私たちきょうだいが知らない、カサブランカよりも好きな花、母の母だけが知っている花。それは、今日、この季節に咲く花だった。

その花の香りに包まれて眠った母は、きっと美しい思い出と共に旅立ってくれたのだと思う。
先日SPBSで実施した批評ワークショップで、ゲスト講師として登壇された桜庭一樹さんの小説『少女を埋める』を読んだ。ちょうど私の母と同じ3月初旬の沈丁花の咲く季節に、主人公の冬子が父を見送る最後の数日間が描かれていた。その空気感がとてもリアルで、あの時の光の色までありありと思い出した。
今日も駅までの道で、どこからか漂う沈丁花の香りが、春の訪れを告げていた。
編集部 K

